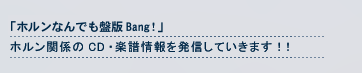| 1. |
モーツァルト: ホルン協奏曲 断章 変ホ長調 K. 370b |
| 2. |
ダマソ・ペレス・プラード/ジョシュア・デイヴィス編曲: Que Rico el Mambo エル・マンボ |
| 3. |
モーツァルト: ホルンと管弦楽のためのロンド 変ホ長調 K. 371 |
| 4. |
エドガー・オリヴェロ: サラナード・マンボ(「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」による) |
| 5~7. |
モーツァルト: ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447 |
| 8. |
ジョシュア・デイヴィス & ユニエト・ロンビーダ・プリエト:ロンド・アラ・マンボ(K. 447 第3楽章による) |
| 9. |
イソリーナ・カリージョ/ホルヘ・アラゴン編曲:くちなしの花をふたつ |
| 10. |
モイセス・シモン/ホルヘ・アラゴン編曲: 南京豆売り ~ライヴ収録 |